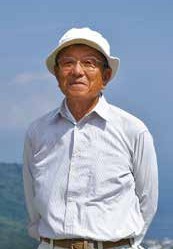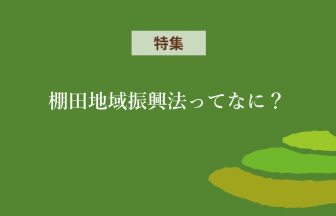2012年から始まった静岡県松崎町石部棚田での当団体のお米づくりプロジェクトが、2024年をもって
終了しました。ここでは特集として、当団体の現地活動の13年の歴史とその意義を振り返ります。
復田の取り組み
保存会との共同プロジェクトがスタート
私たちと石部棚田の本格的な関わりの始まりは、2008年に石部棚田オーナーになった久野大輔(現・棚田ネットワーク理事)が当団体に入会し、数名の会員を引き連れてオーナー参加したことに遡ります。それから全国棚田調査プロジェクトでの調査活動や企業のCSR活動の斡旋、2010年に松崎町で開催された「第16回全国棚田(千枚田)サミット」への協力と、それに伴う石部棚田ホームページのリニューアル作業を担当したことで、保存会や町役場だけでなく集落の方々とも友好的な関係を築いてきました。
そして、当時の保存会初代会長で、石部棚田の復田活動の中心人物でもあった髙橋周蔵さんから私たちにある提案がされたのが2012年でした。当団体のメンバーだけで石部棚田の入り口にある花壇として利用されていた8枚3㌃の棚田を復田して、石部伝統の「蓑口と本畦」のある風景を再現して欲しいというものでした。棚田に上ってくる多くの人たちがまず目にする田んぼが、昔ながらの石部の風景であって欲しいという周蔵さんの強い思いからでした。 それは、田起こし、畦切り、畦叩き、代掻き、畦付け、畦塗り、田植え、草刈り・草取り、稲刈り、脱穀、精米の全作業を私たちが行い、毎日の水の管理、苗の準備、田植え直前の代踏み作業のみ保存会が行うという当団体と保存会の共同プロジェクトでした。
年間を通じての田んぼの作業の経験もなく、しかも都心から車で3時間半をかけてくる私たちにはたして出来るのかという心配もありましたが、まずは一年やってみようと2012年3月3日に、当団体メンバーと保存会総出での復田作業を行いました。
昔ながらのお米づくり
オーナー田との違い・蓑口と本畦がある田んぼ
石部棚田のオーナー制度は、会費三万五千円で約100㎡の田んぼで田植えと稲刈りの体験ができて、20㎏のお米をもらうことができます。その田んぼの田植え・稲刈り以外の作業は基本的に保存会やボランティアによって行われています。 一方、私たちで管理する田んぼは8枚3㌃で年間費五万円(※)。水の管理、苗の準備、田植え直前の代踏み作業以外のすべての作業は私たちで行い、この田んぼで収穫されたすべてのお米をもらうことができます。平均100㎏程度の収穫ができるので、かなり破格の条件ではありますが、当団体としてもそれ以上の予算を捻出するのが難しく、その分私たちが得意とする情報発信の分野で石部棚田の保全に積極的に寄与するという形でスタートしました。 そしてオーナー田とは大きく違うのが、水の落とし口と畦です。石部棚田では昔から、田んぼから田んぼに水を落とす場所に藁束を組んで作る「蓑口」と呼ばれる伝統的な仕組みがありました。現在オーナー田では、手間と修復が必要な蓑口をすべてやめてパイプで代用しています。しかし、蓑口は労力がかかりますが、クッションとして水を受け止め、毛細血管のようにソフトに水を流し落とすので、棚田底部の粘土層である「盤」を傷つけないための先人の知恵でした。また、蓑口は最後には自然に朽ちて田んぼの肥料になるという日本人の自然に対する循環思想の象徴でもあります。 また、石部棚田の伝統的な畦は、三面に付ける本畦(飾り畦)とも呼ばれるものでした。それはできるだけ苗を植える面積をとるため、畦を極力細く二面付けにして、最後にその畦を歩けるように平らにならすための三面目を付ける技法です。こちらもオーナー田では、体験者の安全を考えて畦を幅広くとっているのと、手間を考えてすべて二面付けの略式畦となっています。 これらの伝統的技法を一年目は、地元のおばあちゃんや保存会の方々に教わりながら、見様見真似で米づくりを行い125㎏程のお米が収穫できました。二年目からは、それらの伝統的技法や年間を通した作業が体験できる「昔ながらのお米づくり体験」と銘打ったイベントとして開催しました。
石部棚田での活動
コロナ禍を乗り越えて
イベントに参加してくれたのは一般申し込みの他、スタッフの家族や友人、会社の研修などさまざまで、やはり田植え稲刈り作業は人気があり、平均30人程度の参加者で賑わう一方、草刈り草取り作業は2、3名で行うこともありました。また収穫後の11月には棚田の交流棟を借り切って、その年の新米と石部伝統の呉汁を作って味わう「新米を食べる会」も開催し、地元との交流を深めた結果、オーナー
となって保全に参加する人が出るなど石部棚田の入口としての役割も果たせるようになりました。
転機は2019年の暮れから始まったコロナ禍。2020年は田起こし、畦切りまで行った段階で田植えを断念し、その年のイベントはすべて中止し、スタッフだけで草刈りを行いました。2021年はお米づくりを再開しましたが、全ての作業をイベントとして一般募集する形が難しく、田植え、稲刈りのみを体験イベントとし、その他の作業はボランティアによる少数運営へと切り替えました。
保存会の人手不足
2012年から13年12回のお米つづくりを継続しましたが、保存会初代会長髙橋周蔵さん、二代目会長髙橋靖さんが亡くなり、年々保存会の後継者不足や資金不足が叫ばれるようになりました。蓑口など伝統的なつくりのために、特に毎日の水回りや調整に時間がかかる私たちの田んぼが、現在の保存会に大きな負担をかけていることが表面化しました。またそれを補うオーナー相当の管理費に引き上げる余裕が当団体にもないため、保存会との話し合いの結果、2024年をもって、当団体でのお米づくりブロジェクトを終了することになりました。 参加者のみなさま、そして保存会はじめ、松崎町、静岡県などの関係者のみなさま、私たちの10年以上の活動を支えていただきありがとうございました。当団体としては、今後はオーナー制度などの作業や、棚田協議会などへの協力を中心に引き続き石部棚田のサポート活動を継続していきますので、よろしくお願いします。
◇ 認定NPO法人棚田ネットワーク会報誌「棚田に吹く風」134号(2025年冬号より転載)
https://tanada.or.jp/news/kaiho134/