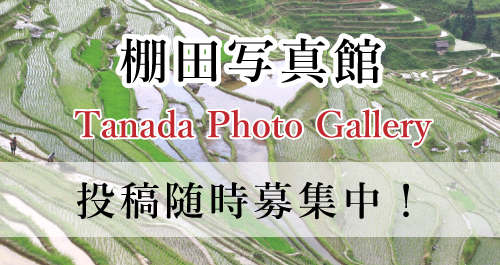棚田は私たちの大切な財産
山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に造られた水田。畦(あぜ)の重なる形が棚に似ていることから「棚田」と呼ばれるようになりました。日本では、山がちのところではどこにでも見られる水田形態で千枚田とも呼ばれています。その中でも、人の目に触れることの多かった能登白米や信州姨捨の棚田はよく知られ、その景観の美しさが文学作品にも描かれました。この風景は、訪れる多くの人が「懐かしい」と感じる日本の原風景であり、私たちの祖先の知恵がぎっしり詰まった、大切な財産でもあります。一方、最盛期22万haといわれた棚田も減反政策や農村人口の減少、高齢化等により耕作放棄が急速に進みました。このような棚田の荒廃を鑑み、棚田地域の振興を目的に令和元年(2019年)には「棚田地域振興法」が制定されました。関連して「つなぐ棚田遺産」として全国の棚田271ヶ所が選定されました。直払い加算などが加味され棚田地域の活性化の切り札ともいえる「つなぐ棚田遺産」選定地の総面積も6千5百haほどであり、極めて貴重な文化的価値を持つ存在となっています。
石川県輪島市の白米千枚田
耕作放棄される棚田
棚田は、平坦地の水田に比べて「労力は2倍、収量は半分」といわれます。労働・土地生産性の低さから、米余りによる生産調整(減反政策)が始まった1970年以降、棚田の転作・放棄が見られるようになりました。当初は、農林水産省の政策で主に杉林へと転換が促されました。その後、棚田地域では過疎・高齢化が進み、耕作の担い手ばかりでなく住民そのものがいなくなり、耕作放棄は止まらず集落そのものも小規模・限界集落(住民の半数が65歳以上)となり、消滅の危機が問題となり始めました。
保全活動の始まり
1995年以降、イギリス人写真家ジョニー・ハイマスや今森光彦の棚田写真集の出版を皮切りに、棚田への再評価が高まります。棚田が荒れていく状況をなんとかしようと、高知県梼原町では「第1回全国棚田(千枚田)サミット」が開かれ、棚田関係者をはじめ市民や研究者など1200人以上が参加しました。全国的な保全団体の発足や、各地で棚田オーナー制度がスタートするなど、1995年は棚田保全への社会的意識が高まった「棚田ルネッサンス」の年といわれます。
一つとして同じではない棚田の形
棚田は定量的には20分の1以上の傾斜地に築かれた水田ですが、形はさまざま。その地域の古いにしえの人々が、山の形、産出する土や石、そして水の流れという自然に寄り添いながら、連綿と築き上げてきたからこそ、一つとして同じ形はないのです。
- 鴨川市大山千枚田
- 有田川町あらぎ島
- 吉賀町大井谷
- 日南市坂元
注目される 棚田のさまざまな機能
水のきれいな水源に近く、昼夜の温度差が大きい「棚田」は、おいしいお米を育てます。また、多種多様な生き物を育む生態系の宝庫であり、地滑りや洪水、表土の流出を防ぎ、地下水を蓄えるなど、国土や環境を保全する多くの機能を持っています。棚田は米作りの場としての機能だけでなく、人や環境にとって有益な「多面的な機能」があることが注目されています。

愛媛県内子町の泉谷棚田
人と生き物、そして自然を繫げる棚田
棚田には、用水と排水を兼ねた水路や、土で作られた畦が残っていて、生き物が成長に応じて田んぼと水路を行ったり来たりすることが可能です。溜め池や湿田などの水たまりも多く、周囲の自然環境との補完性、水質の良さなどの理由から、多種多様な小動物、昆虫、植物が複雑な生態系を築き上げています。人と生き物、そして自然が無理なく調和した棚田のシステムには、私たちが未来を築くヒントがたくさん詰まっているのです。
日本人の心の継承の場として
全国で行われている棚田オーナー制度では、手植えや手刈りでの稲作体験ができます。昔ながらの農法を実践するところも多く、伝統的なお祭りや神事が残るところもあります。最近は、畦に明かりを灯し自然に感謝するイベントなども行われ、棚田は美しい原風景とともに、日本人の心を継承する貴重な場としての存在感を高めています。

長野県上田市の稲倉の棚田